先日、t検定について復習した記事を書きましたが、今回はその続きで 「回帰分析」 のお話です。
(t検定の記事も、よかったら読んでみてくださいね♪)
わかったつもり、になりがちだからこそ…
いろんなことを学ぶと、「なるほど、わかった!」って思いがち。でも、自分の言葉で説明しようとすると、意外と言葉が出てこない…。 そんな経験ありませんか?
私もまさにそれで、「これはまだちゃんと理解できてないな」と感じることがあります。
だからこそ、自分だけがわかればいいメモ ではなく、誰かに読んでもらっても伝わるような言葉でまとめてみよう! と思って書いています。
回帰分析とは?
簡単に言うと、
1つまたは複数の「理由(=変数)」から、「結果(=変数)」を予測する分析方法です。
たとえば、「テストの点数」という結果が、「勉強時間」や「睡眠時間」などの理由で決まっているとしたら、それを数式にして表せるようにするのが回帰分析です。
専門用語で言うと…
-
独立変数(説明変数):理由となる変数(例:勉強時間、睡眠時間)
-
従属変数(目的変数):結果として予測したい変数(例:テストの点数)
単回帰分析と重回帰分析の違い
単回帰分析
→ 独立変数が1つ の回帰分析
例:「子どもの身長から、体重を予測したい!」
-
身長(独立変数)
-
体重(従属変数)
重回帰分析
→ 独立変数が複数 の回帰分析
例:「子どもの身長と年齢から、体重を予測したい!」
-
身長と年齢(独立変数)
-
体重(従属変数)
回帰分析の流れ
回帰分析では、独立変数(理由)と従属変数(結果)との関係を見つけて、数式にまとめていきます。
たとえば…
「1時間勉強すると、テストの得点が10点上がるらしいぞ…?」
というルールを見つけるような感じです。
これを数式で書くと:
テスト得点 = 50点 + 10点 × 勉強時間(時間)-
50 → 切片(勉強しなくても取れる点数)
-
10 → 回帰係数(1時間あたりに得点がどれくらい上がるか)
この関係を グラフ にすると、真っ直ぐな線(回帰直線)が引けます。
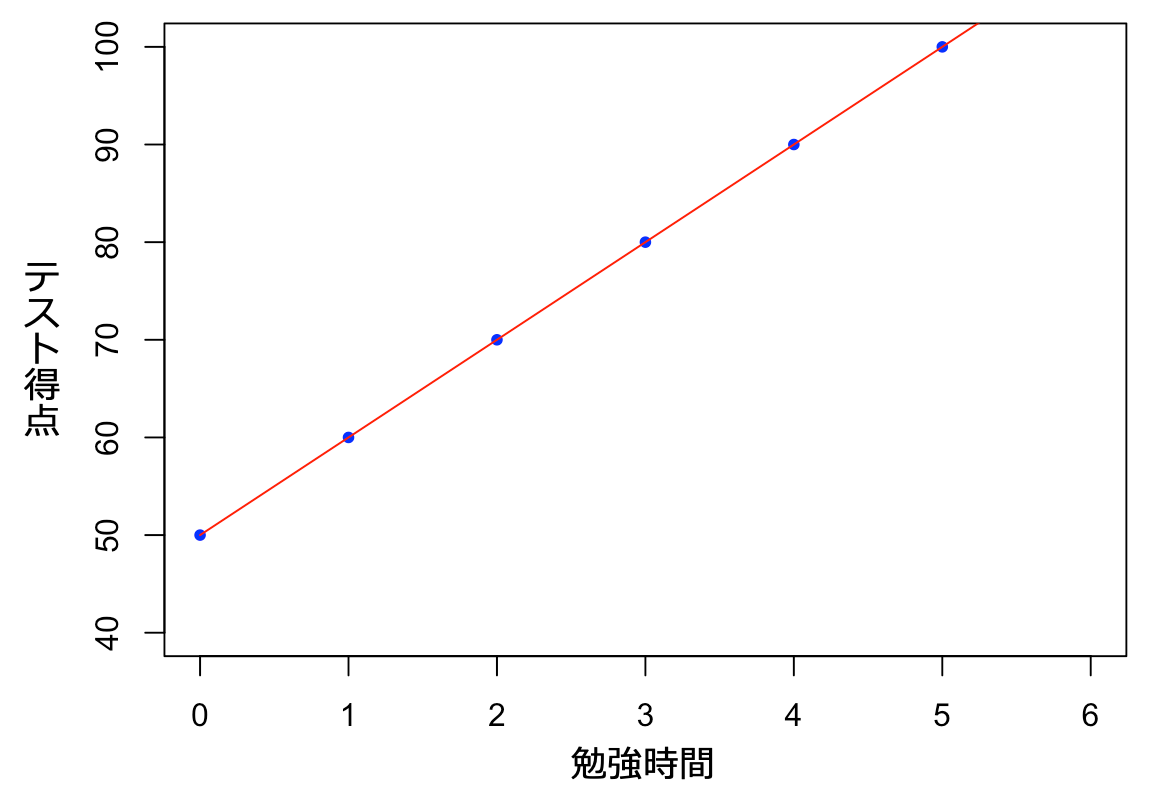
さらに深く見ると…
この回帰直線がどれだけ「当てはまっているか」や「信頼できるか」を調べるために使うのが、以下の指標です。
● 決定係数(R² / アール二乗)
→ 予測(モデル)がどれくらいデータをうまく説明できているかの指標
→ 0〜1の間の値で、1に近いほどピッタリ!
● p値
→ その関係がたまたまじゃなく、本当に意味があるかどうか
→ 小さいほど(たとえば0.05未満)信頼できる関係だと言えます。
覚えておきたい基本用語まとめ
|
用語 |
説明 |
|---|---|
|
従属変数(目的変数) |
予測したい結果(例:テスト点数) |
|
独立変数(説明変数) |
原因・理由となる変数(例:勉強時間) |
|
回帰式 |
変数間の関係を表す式(例:点数=5×時間+30) |
|
切片 |
独立変数が0のときの目的変数の値(30) |
|
回帰係数(傾き) |
独立変数が1増えると目的変数がどれくらい増えるか(5) |
|
単回帰分析 |
独立変数が1つの場合の分析 |
|
重回帰分析 |
独立変数が複数ある場合の分析 |
|
残差 |
実際の値と予測値との差 |
|
決定係数 R² |
どのくらいモデルがデータをうまく説明できているか (1に近いほど良い) |
|
p値 |
偶然かどうかの指標(0に近いほど関係が確か) |
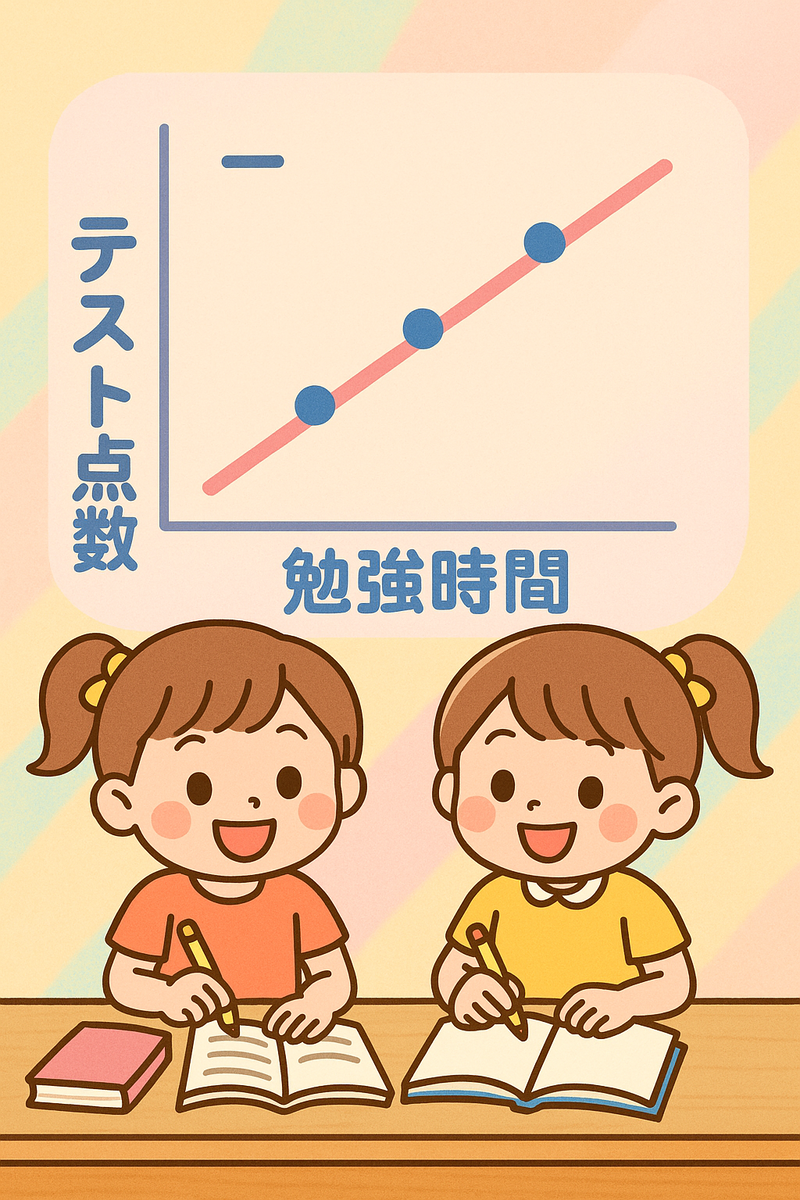
おわりに
「なんとなくわかった気になってたけど、説明しようとすると難しい…!」
そんな回帰分析も、仕組みを少しずつ整理していくと、意外と楽しく学べます✨
次回は、この回帰分析と分散分析の違いについて、まとめたいと思います!